
お母さんが元気なら子供も元気になると言われても、ひきこもりの子供を見て元気になれません。



お母さんの気持ちは当然です。むしろお母さんの心配な気持ちが、解決の糸口を探す突破口になります。
親の焦りをひきこもり克服の力に変える
子どもが引きこもりになると、「早く元の生活に戻ってほしい」と焦りや不安を感じることは自然な反応です。
しかしその焦りが子どもへプレッシャーとなり、事態が悪化する場合もあります。
親自身が焦りと向き合い、子どもの自立を支援するための心構えについて考えてみましょう。
焦りは親として自然な感情
親というものは、子供の明るい人生に希望をもって子育てをしてきたのです。
レールを外れてしまった、元の元気な姿に戻れるのか、自立できるのか、心配でたまらないのは当たり前のことです。
- 子どもの問題を切り離しましょう
- 様子を見ましょう
- 親が元気でいるのが一番
上記のことはよく言われることで、もっともなのですが、単に子どもの問題だと切り離せば、実はひきこもりの裏に重要な課題があることに気づかないかもしれません。
10年前、突然ひきこもりになった娘や、どん底の葛藤を味わった息子を前に、深い絶望にいた当時の私には見守るだけでは解決策になりませんでした。
母親として経験しなければ、あの真っ暗闇の絶望感は分かりません。


焦りが子どもに与える影響
ただ、親の焦りを子どもにぶつけたりすれば、子どもはプレッシャーを感じたり、「自分は期待に応えられていない」と感じ、自信を失ってしまいます。
焦りの代わりに、自分の感情を見つめ直し、子どもの良さ、今まで頑張ってきたことを書き出してみましょう。
私たちも子ども達も皆、輝くために生まれてきています。子どもと向き合う姿勢を整え、子どもの良さと将来を信じることで、思考と言葉が変わります。
私達母親として焦りは当然なのです。
その深い愛情こそが、子どもが再び元気に歩み始める働きかけに、変えることができます。絶望感を大きなチャンスに変えましょう。


共感から始める自立支援のアプローチ
学校に行けないことは甘えなのか
学校に行けない状態は、自信が大きく減っており、決して甘えではありません。
子どもは何とかして頑張ろうとしています。それでも、勉強に向かえない、教室に入れない、人に会えない。まず、この葛藤を理解してあげることが大切です。
この場合は、一旦学校も休んで親が子どもの気持ちに寄り添い、共感を持って接するほうが子どもの気持ちも落ち着きます。
親子の信頼関係を築く



子どもに行けない理由を聞いても答えません。
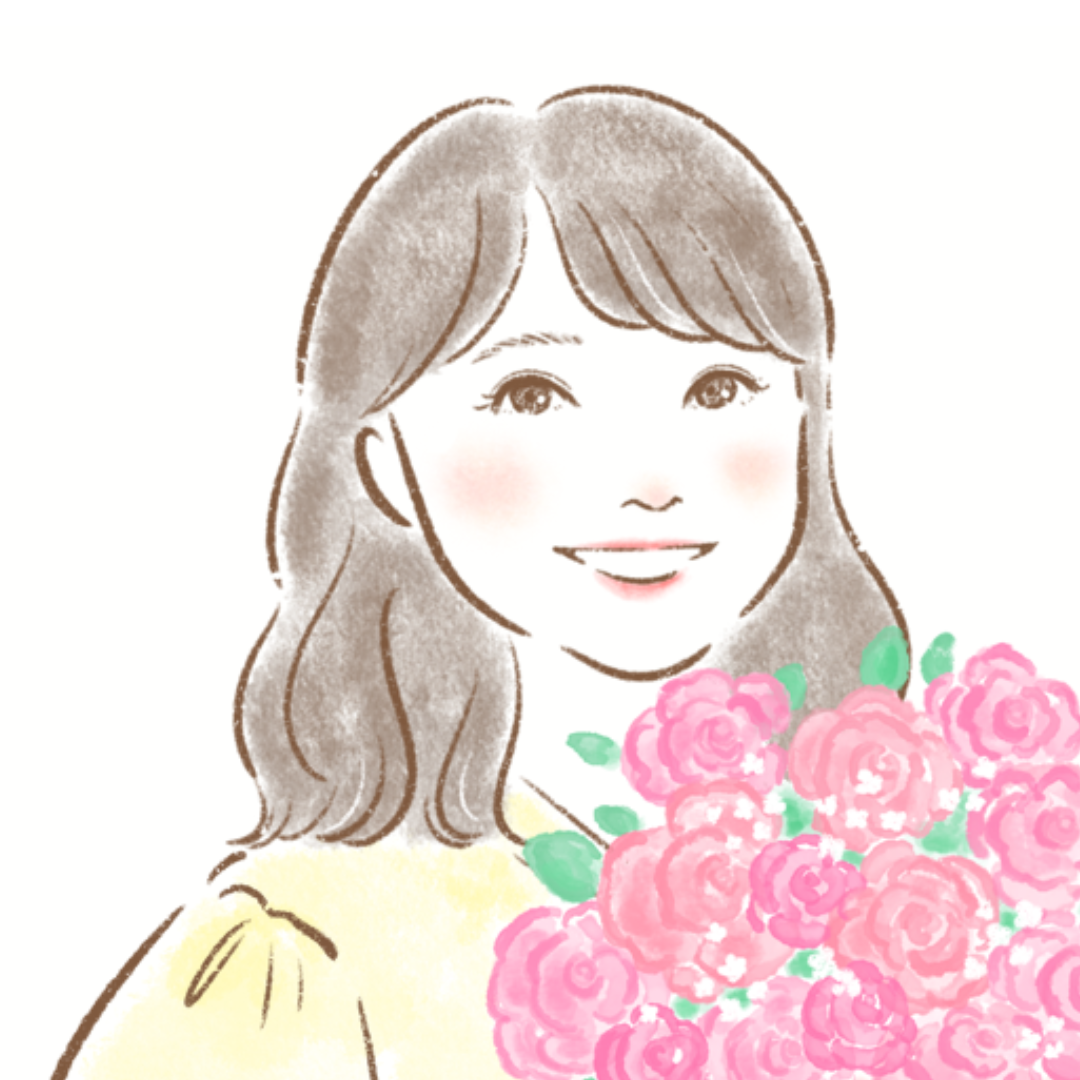
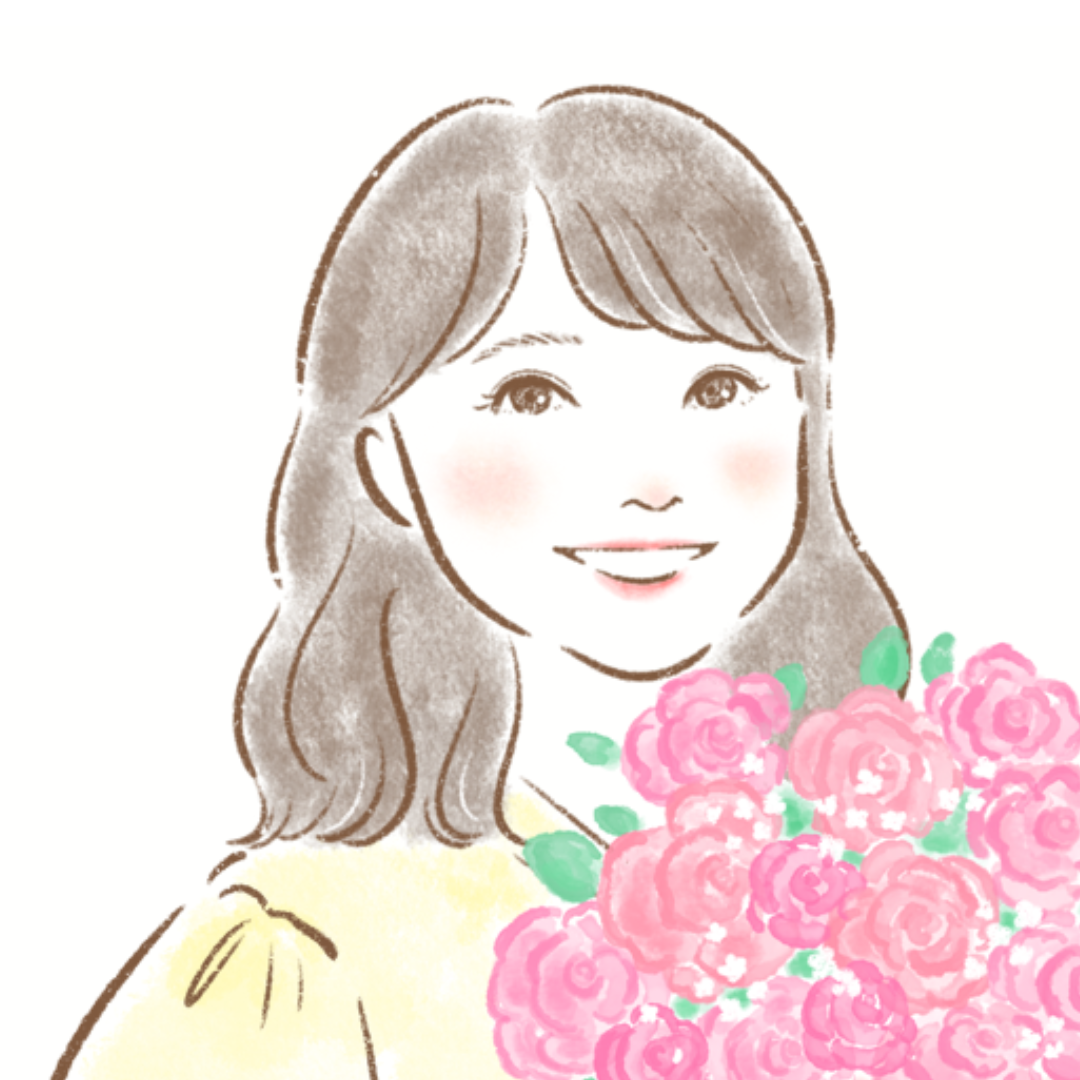
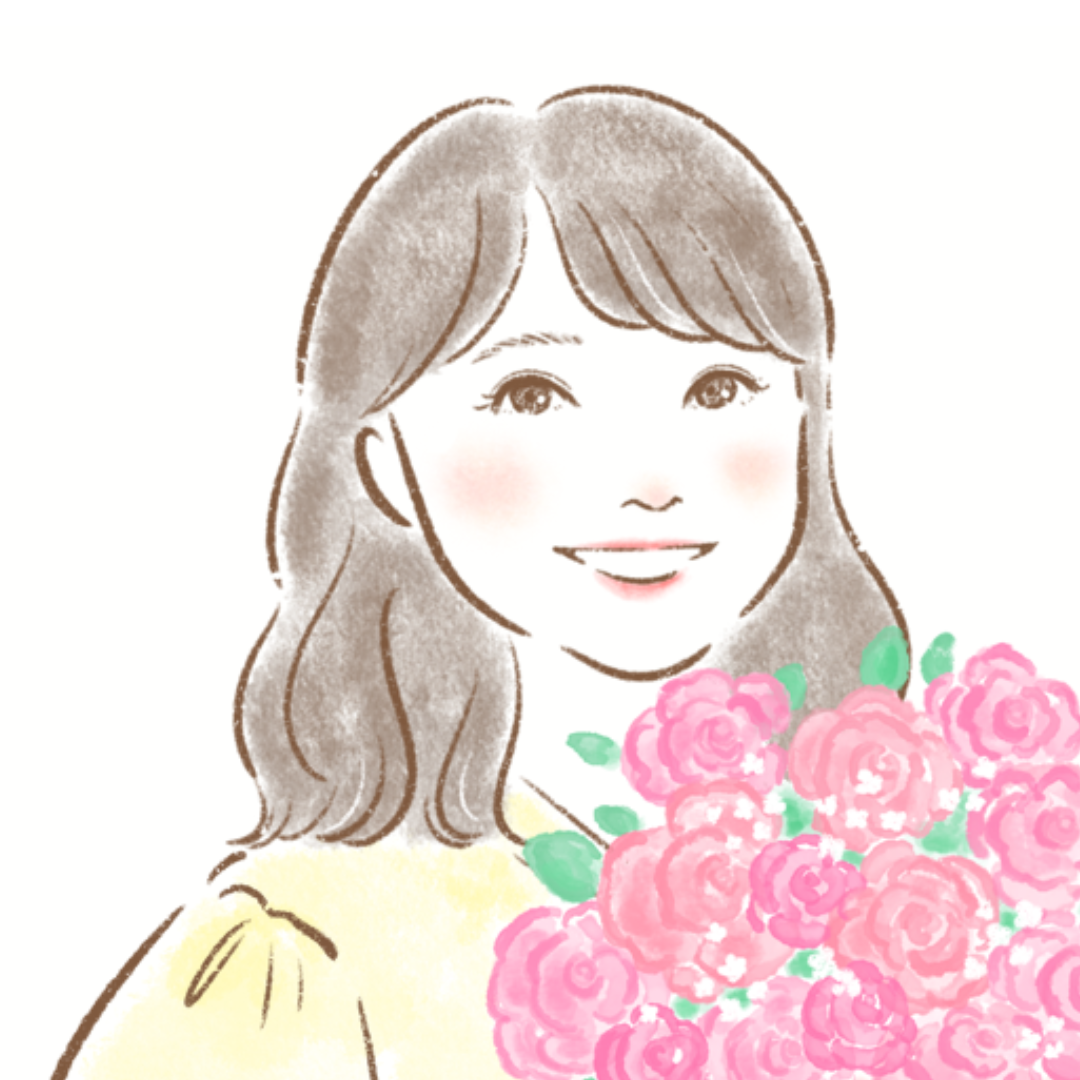
子ども自身も、行けない理由が分かりません。責めの代わりに、言葉でも手紙でも、愛情を伝えましょう。
ひきこもった年齢や背景がみんな違っていても、親としてやれることは共通しています。それは、まず親子の信頼関係を築くことです。
そして何よりも大切なのは、愛情を言葉で伝えること。焦りは子供への責めになります。



愛情を言葉で伝えようとしたら、考え方ががらりと変わりませんか?
学校に行けなくなるまでに、自信は見えないうちに減り続け、全て自信というエネルギーを使い果たした時、行動が全て止まります。学校へ行けないということは、それだけ異常事態だということです。
突然の不登校に、親としてはパニックになると思いますが、子どもの異常事態を理解しておけば、かける言葉が変わります。
たとえ子供が原因を何も話さなくてもいいのです。子ども自身が原因が分からないことが多いからです。
- 大変だったね
- 頑張ったね
- 生まれてきてくれてありがとう
いろんな言葉がありますが、子どもの心に響く言葉をかけましょう。
子どもは自分の気持ちを理解してもらえることで安心感を得て、親との信頼関係を築くことができます。時間はかかりますが、そこから全てが始まります。
小さな変化を見逃さない観察力
お母さんが元気で挑戦していれば、子どもも挑戦が始まるという意見もありますが、絶望の淵から気持ちを切り替えて挑戦するなど、私にはとてもできませんでした。
それよりも、まず親としてやれることがあるはずです。子どもは愛情を求めて寂しさで一杯かもしれません。



子どもの小さな変化、気づきを観察しましょう
もちろん私達親も、気分転換が必要です。と同時に、子どもに何か変化がないか、目のはしに入れておくことがとても大切です。起きて、今日も食べれた、たとえそれだけでも喜んで伝えること。
そして、子どもの言葉に大きくあいづちをうつことが、自信を増やしていきます。
自信を入れるのは毎日の積み重ね。これは親しかできないことなのです。
なかなか事態が変わらない状態が続くと親も投げ出したくなりますが、ここで土台を築き直せば、子どもの人生が大きく変わります。一時の辛抱です。私も何度も「もう無理!」と思いました。
でも支えられるのは私だけ。
そう考えて何度も奮い立たせました。長い間ひきこもりで人が怖いと泣いていた娘は今、日本の技術を世界で売る営業として、自分の挑戦を楽しんでいます。
また息子は思春期の試練や葛藤を乗り越え、今は大学院で未来の可能性と人との出会いにワクワクしています。
あれがあったからこそ今がある。これから未来は明るくなると信じて、子どもに自信を入れていきましょう。


共感は子どもの自立を促す



愚痴、つぶやき、気づきを途中でさえぎっていませんか?アドバイスよりも、最後まで聴いてあいづちをうつ威力は大きく効いてきます。
親が共感を持って接することで、子どもは安心して自立に向けた意欲を高めることができます。
ひきこもりの状態は、自信がすっからかんになくなった状態。
そこに自信を一滴一滴入れていくのです。聴くこと、共感だけでも、「親は聴いてくれた」と、少しずつ自信がたまっていきます。
自信は目に見えてたまりません。でも、我が家の子ども達も、生徒さんも、聴いて自信を増やすことで行動が始まりました。どの生徒さんも、感動的なシーンでした。


親自身の心構え 親としてできること
子どもが引きこもりの状態にあると、親としての不安や焦りが募るものです。しかし、子どもは一朝一夕には変わりません。
まずは親としてできることから始めてみましょう。ここでは、親が自身の感情と向き合い、親としてできることをご紹介します。
子育ては失敗ではない
まず親自身の感情や過去を振り返ることで、冷静な対応が可能になります。
子育ては失敗だったのか、と全てを否定したくなります。私も「どこで失敗したのか。」と、元気いっぱいだった昔の子供たちを振り返り、当時絶望感しかありませんでした。
でも、親として良かれと思ってやってきたことがどうなるのかなんて、誰にも分りません。
過去はいいんです。これからひっくり返せば親子共々、全ての葛藤をプラスに変えられます。今気づいて振り返る勇気が、起こったこと全てを財産にできます。
【世代間連鎖】と【子どもの良さ】を振り返る
素敵なノートとペンをもってカフェなどに行き、まずは【ご自身の親のこと】を振り返ってみましょう。子育ては、実は世代間連鎖が大きく影響している場合があります。
- 「大丈夫?」「気を付けて」先回りの口癖
- 怒りだすと止まらない
- 自分の親からの愛情を感じられなかった、寂しかった
親の口癖や考え方を、知らぬ間に受け継いでいるため、過干渉や心配性、子どもへの愛情の伝え方などが理由で、不登校やひきこもりがおこっていることも多いのです。
【小さい頃から今までの子どもの良さ】も書いてみましょう。
- 頑張っていたシーン
- 優しさ、粘り強さ、責任感など
- 子どもが好きなこと、口にしていた夢


書き始めれば膨大に出てくるはずです。
親が愛情や子どもの良さを言葉で伝え続けることで、子どもの本来の強みが出てきます。
カフェなど場所を変えて自分との振り返りの時間をもつことで、新しい見方に気づきます。
第三者に話すことが、新しい見方につながる
10年前、子どもの様子がどんどん悪化してひきこもる様子に、何から始めたらいいのか当時の私はパニックになりました。でも、探し当てた言葉の専門家に相談し、「大丈夫です、元に戻ります」の言葉に、大きな勇気をもらいました。
ひきこもりの原因は、様々な要因が複合的にからみあっています。世代間連鎖の問題もあり、決して私達親だけの問題ではないのです。振り返れば、子どもが身をもって教えてくれた、と思っています。
私は10年の我が家の試行錯誤から、お子さんへの見方や強み、大きな可能性をお伝えしていきます。私がお子さんの未来を信じることで、親御さんへ自信を入れ、その親御さんの自信が、お子さんへ入れる自信になります。
自信の好循環は、大きな変化をもたらしていきます。
まずはお気軽にご相談ください。光はもうすぐです。








