不登校、ひきこもりに解決の道はあるのか。子どもを信じてと言われても、どう信じればいいのかと、渦中にいる親は思います。ひきこもりの克服や、社会に出て役にたつことは、幼少時からの得意なこと、好きなことにヒントがあります。ひきこもりだった娘の克服を振り返り、必ず希望はある道をご紹介します。
ひきこもりを克服した娘が社会に出て生かしたこと
子供の好きなことが将来どう役に立つのか、先が見えない状況ではなかなかわからない。わからないどころか、親にとっては、できないことの方が目についてイライラしてしまいます。でも、必ずある子供が好きだったこと。好きなこと。なぜか気になること。実はそこに、子供の人生のストーリーが隠されているとわかりました。
夫の駐在で家族で海外にいた時、娘は夢と希望をもって転校した高校で、クラス中から存在を無視されるという人種差別のいじめをうけました。それが重症のトラウマとなり、人と全く会えず、2年間ひきこもりになりました。その間、親の言葉かけを学んで娘に自信を入れることを必死で続けました。先が見えない暗闇で見えたことは、
学校の成績で評価されないけれど得意なこと。それが仕事に大きく生きること、に気づきました。
折り紙
娘は幼稚園、小学校1年生など幼少時に折り紙が得意で大好きでした。暇さえあれば、難しいバラなどをささっと作り、まわりにプレゼントしては喜んでいました。学校の勉強は全くできず、計算も文章も書けずに宿題を目の前にして空をただただ見つめる、そんな日々で、私は毎日心配で仕方がありませんでした。金切り声で急がせていた記憶しかありません。でも勉強の能力は全体のほんの一部。折り紙の出来上がりをささっとイメージする空間のイメージ力は後に大きく力になると知っていれば、当時の私も安心したはずです。
ひきこもりを克服し、光や装置を組み合わせてシステムを構築する技術の会社に入り、研修ではパパっとイメージで操作ができ、大変驚かれました。高校時代ひきこもりのために理系の勉強は殆どゼロだったにもかかわらず、人の能力とは切り口次第でいろんな力がでてくるものだと驚きました。
出来上がりをイメージして把握する力。空間を把握する力、イメージする力。そんな幼少時の力は、社会人の今、カメラで表現すること、会社紹介の動画作り、仕事のチラシ作りなど、表現の手段は変化していきました。

パソコン~パワーポイントで見せる力
駐在の時、小学校でパソコンの授業がありました。小さい時から機械の操作を始めると、子供は慣れるのに早いのでしょう。図を入れて説明する、人への見せ方、切り口に慣れていました。今、娘は出張報告として、どうやったら人に伝わるか、表現の方法、見せ方を工夫することが得意です。同じ説明をするのにも、パソコンで図解を駆使するプレゼンが得意ならば、これは働く上で一つの大きな武器になります。

韓国料理で人をつなぐ
ひきこもり中、人に会えず、ひたすら家で過ごすしかありませんでした。将来に希望をもてず、目は常にうつろでした。でも韓国大好きな娘は、ささっとお惣菜を作ったり、韓国風太巻きを作って家族に喜ばれていました。2年間の辛いひきこもり中、なんとか自信をためて勇気をふりしぼって大学に入ると、ひきこもり中に作っていた料理で人を集め始めました。
「ラーメンでも食べにこない?」大学の寮では声をかけ、孤独な留学生は大喜びで集まり、人をつなぐ武器となりました。自分の料理で人が喜んでくれる。これはまだ人に対する恐怖で不安定だった娘に、たくさんの自信を与えてくれました。料理が得意。必ずしも直接料理の道に行かなくても、自分を再び輝かせる大きな武器となりました。

動画編集スキル
折り紙で発揮した表現する力は、後にYoutubeで発信する力になりました。カメラで動画を撮影し、編集ソフトを独自で学び、見せ方を工夫していきました。Youtubeは質問が殺到して今は止めていますが、またコンセプトを変えて自分を表現したいと考えています。
動画撮影、動画編集のスキルは、会社で大いに役立ちました。展示会では自社の製品を紹介する短編動画を作り、大変喜ばれました。外注よりも、内情を知っている社員がささっと作ったほうが、つたないながら説得力があります。商品のチラシ作りも得意です。チラシは、人が見てどう思うか、見せ方を工夫することがで上達しました。好きなことには時間も忘れ、あれこれ機械操作をしているうちに、スキルが伸びていきます。
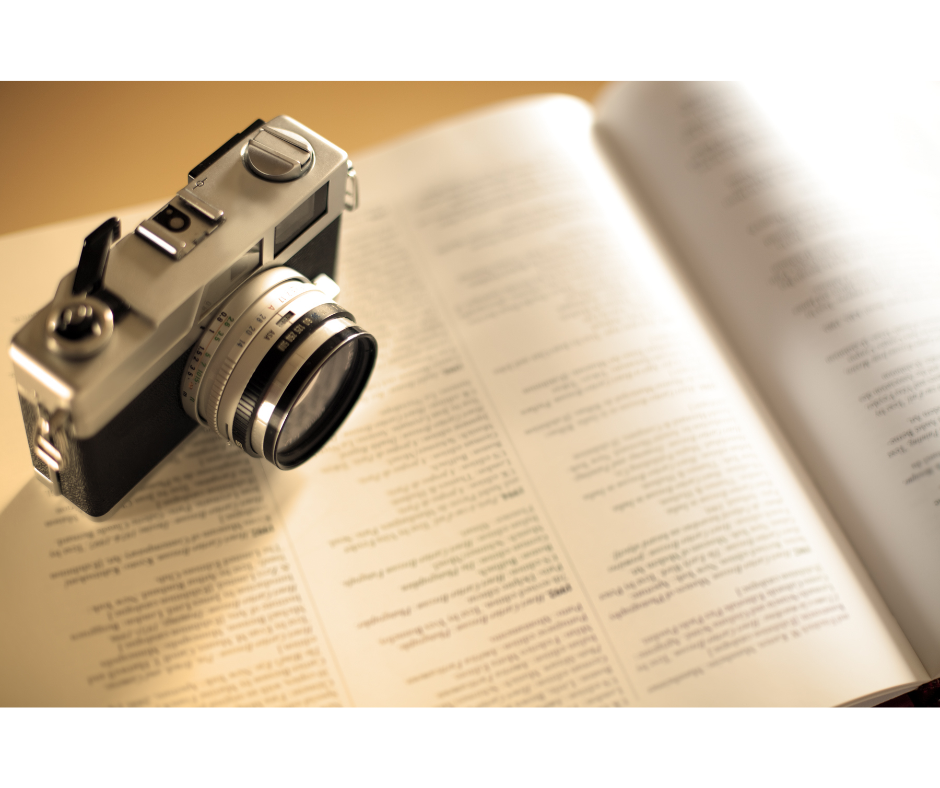
学校に評価されない強みを見つけよう
娘が高校時代ひきこもりだった時。勉強に手がつかず、教科書を広げられませんでした。私が心配なことは学校に関係すること。娘が得意なこと仕事に役立ったことは、学校の評価にのらないこと、でした。
この、学校の評価にのらないけど、娘が得意なこと。まさにこれが、今ようやく、仕事で強みになってきたのです。学校では、短時間で大量に暗記してテストでアウトプットする、という力が求められますが、娘が得意なことには、共通点がありました。
*人に見せ方を工夫すること
*立体的にとらえる力です。
立体的にとらえる力は理系でなくても、会社の技術を学ぶのに大いに役立ちました。見せ方を工夫する力は会社の展示会、動画で報告など様々なシーンで役立ちました。抽象的な力、ですが、会社では実に大切になる、と今わかりました。
観察すれば力が見える
子供をよく観察すると様々な力を見つけることができます。もちろん、それがどう将来に展開するのか、社会人にならないと分からないので、子供が自立する前や特に不登校などの時は、焦りばかりが先に立ちます。でも、そこをぐっとこらえ、勉強以外の強みをじっと観察して伝えていきましょう。それは大きな自信となり、やがて自分を生かす柱になります。柱が何本もあれば、社会に出よう、人に会おう、そんな勇気がわいてくるのです。
親ができることはひたすら良さ、強みを伝えること。話を聴き、大きくあいづちをうってあげること。子供はやがて、自分の使命をみつけて羽ばたいていきます。
ぜひ、お子さんの力をたくさん伝えていきましょう。
夢を持って社会に出ていく、自信とスキルを磨きましょう。








